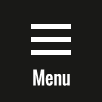福岡・博多は日本で最初にまんじゅうが伝来したところといわれます。博多駅前1丁目の承天寺(じょうてんじ)の開祖・聖一国師(しょういちこくし)が、中国・宋にわたってさまざまな技術を身につけ、持ち帰ったうちの一つがまんじゅうの製法だったとか。そんな福岡の地に、名物となる夏限定の和菓子が誕生しています。その名も「博多水無月(みなづき)」。

今年で創立60周年を迎える福岡市和菓子組合には現在60社が加盟、そのメンバーの中から有志が集まり結成されたのが「新福岡・博多の和菓子開発研究会」、100年後でも定番として残っているような和菓子を開発しようという心意気で開発されたのが博多水無月なのです。この和菓子が生まれたのは1999年、今年で12年目を迎え、今ではこの博多水無月の発売を心待ちにしている人たちも多いようです。アズキとわらび粉を主原料として笹の葉で巻かれたもので、これにアレンジを加え、抹茶味、ミルク味なども開発されています。
水無月というのは6月の名称ですが、これはもちろん旧暦のこと。京都では1年のちょうど折り返し地点となる6月30日にこの「水無月」を食べて夏を乗り切る風習が今でも続いています。全国の住吉神社で、夏の無病息災を祈願する「夏越(なごし)祭」が行われますが、福岡でも博多区の住吉神社で、7月30日(金)~8月1日(日)に「名越大祭(なごしたいさい)」(住吉神社では夏越ではなく名越と書きます)が行われ、博多水無月が数量限定で販売されるようです。福岡市和菓子組合の研究会加盟店でも7月31日まで限定販売。これを食べて、夏を元気に乗り切りましょう!
ちなみに住吉神社というのは、全国に2,129社あるそうですが、そのほとんどが海の側にあり、現在では、大阪の住吉大社、下関の住吉神社、そして博多の住吉神社が日本三大住吉といわれている歴史ある神社なのですよ。
Originally published in Fukuoka Now magazine (fn139, Jul. 2010)