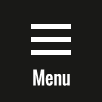全米で話題になったある映画がもうすぐ日本で公開されるのをご存知だろうか? その映画は「ロスト・イン・トランスレーション」。かのフランシス・コッポラのまな娘、ソフィア・コッポラの監督第2作だ。東京の街を舞台にしたこの作品、かのアカデミー賞では4部門にノミネート(脚本賞を受賞)、ゴールデングローブ賞も3部門獲得し、批評家からは絶賛の嵐、興行成績も絶好調、と本国ではものすごいフィーバーぶりで迎えられているのだ。じゃあ、映画で描かれている日本の地でもトーゼン大盛りあがりでしょう!と思いきや、あれれ?なんか意外と、ジ、ミ…??? アカデミー賞大好き!な国にしては、東京での上映も単館のみということだし、福岡で観ることが出来るのはいまのところシネテリエ天神でだけ。(注:3/20現在)同じく日本をキーワードにした「ラスト・サムライ」や「キル・ビル」が莫大な広告予算をかけ、出演陣勢揃いで銀座でのオープニングを飾ったり、多くの劇場で上映されたりしていたのに比べるとなんだかちょっとさみしくない? これって果たしてどういうこと? 今回は映画の公開を記念して、”「ロスト・イン・トランスレーション」ロスト・イン・ジャパン”(わかりづらっ!)、というのをアメリカ人的フィルターを通して考えてみた。日本のあなたの感想は?
さて、まずは「ロスト・イン・トランスレーション」が上記の他の2本に比べ、ちょっと毛色が違うというこの事実。これには映画のジャンルというか作品の性質が大きく絡んでいると考えられる。簡単にいうと「ラスト・サムライ」は時代劇調、「キル・ビル」には日本のアニメ的なアクションシーンが満載、とそれぞれ日本人お馴染みのジャンル、テイストが盛り込まれていてなんとも親しみの沸くつくりなのだ。でも「ロスト・イン・トランスレーション」は言うなればアメリカン・コメディ。ご存知のように、異なった文化の間でユーモアを正確に翻訳し、共有することはなかなかに難しい。
その証拠に、この作品において外国人が最も面白いと思う部分が、逆に日本人の観客には最も理解しがたい部分だったりする。たとえば主演のビル・マーレイが東京のスタジオでウィスキーのCM撮影をするシーン。CMディレクターがどなりながら、ビル・マーレイに対してオール日本語で指示をとばす。いかにもギョーカイ人っぽく(ひと昔前の、って感じだけどね…)中途半端に英単語を織り交ぜてまくしたてるCMディレクター。主人公のように日本語ちんぷんかんぷんの人間にとっては、すっかり訳がわからなくなって、「××××××フォーカス!」「××××××フレンズ!」としか聞こえない。実はアメリカでは、この場面の日本語に字幕が付かない。よって英語圏の観客は彼と同じように混乱し、あたかも”ロスト”したかのような感覚に陥る。監督ソフィアは”ロスト”疑似体験を作品の随所に盛り込み、それがこの作品のおもしろさのベースとなっているのだ。CMディレクターの台詞の内容が丸わかりな日本人観客にとっては、まったく意味をなさない仕掛けなわけだが…。
一方、この映画がちょっと差別的である、という意見も多く出されている。本作のなかの日本人は、LとRがうまく発音出来ない人たち、というおもしろおかしい描き方をされていて(それって出っ歯、メガネ、とかと同じくらい古典的でない?)、誰も意味のある役を与えられていない(マシュー南以外は!)。アジア系アメリカ人が開設する”Lost-in-racism.org”というサイトでは、日本人は薄っぺらいステレオタイプとして描かれていると言っている。あるイギリス生まれの日本人批評家にいたっては、映画のなかの日本人の役割を”安ホテルの汚い壁紙”とまで言い切っている!(その例えのほうがよっぽどひどい気がするけど…)
でも日本に住む外国人でこの映画を見たひとは、自分も似たような体験をしたことに思い当たることだろう。脚本も手掛けたソフィアは実際に日本で”ガイジン”デザイナーとして滞在し、ファッションブランドを展開していたことがあり、その時の実体験がもとになっているからだ。
この作品が日本人差別だという意見に反論すると、実はこの作品は日本人を笑っているのではなく、バカにされているのは主人公の方なんじゃないか(東京の街で”ロスト”しっぱなしで周りの誰にも相手にされない)、という見方も出来ると思う。これはいわば逆転の発想だ。
もし日本の映画会社が日本版”ロスト・イン・トランスレーション”を制作したとする。出て来るアメリカ人は、全員カウボーイハット着用、ハンバーガーばっかり食べてぶくぶく太ってて、ちゃんとセリフがあるのはレスラーのハルク・ホーガンだけ(この作品におけるマシュー南のように)、というようなシチュエーションだったりしたら、それを見たアメリカ人観客はやっぱりあまりいい気はしないんじゃないだろうか。
映画が実際に撮られたその土地でヒットするかどうか、それは難しい問題なんだとは思う。けれどもそれらを差し引いても、「ロスト・イン・トランスレーション」は見るひとの立ち位置によって見え方、楽しみかたが変わる、実はとんでもなく深くてユニークな作品なんじゃないだろうか。あなたの立っている場所からこの作品はどんな風に見えるか、ぜひとも体験してみて欲しい。
************************************************************
ロスト・イン・カルチャーギャップ
日本が登場する映画作品とそこに生まれる”カルチャーギャップ”とは? 福岡在住の映画評論家キネ万太郎氏がそれらの映画のなかの”カルチャーギャップ”について大いに語る! カルチャーギャップを百倍楽しむ法。これを読んでいますぐビデオショップにレッツラゴー。
登場人物が背負う文化のズレをネタにして笑いを生み出すカルチャーギャップ・コメディ。最近では「マイ・ビッグ・ファット・ウェディング」が秀逸だった。ごく普通のアメリカ人男性がギリシャ系女性と結婚することになり、みんなにツバ吐きかけられる(実は魔除けの意味)。彼女の父親はヤケドにも傷にもウィンデックス(窓拭きスプレー)が効くと信じてる。母国では当然でも外国じゃ笑いのネタになる。
今や知事になってしまったアーノルド・シュワルツェネッガーがロシア人将校に扮し、アメリカに逃げたソ連の犯罪者を捕まえにくる映画「レッドブル」。安ホテルに泊まった彼がテレビをつけると、ポルノを放送している。ロシア人将校は言う…『資本主義め!』。ソ連なき今、こんなギャグも生まれない。東と西のカルチャーギャップは確実に消えていきつつある。
同じ国でもカルチャーギャップはある。森田芳光監督の「おいしい結婚」って映画では、カップルがお好み焼きの焼き方でモメていた。卵を生地に混ぜこむのか、別に焼いて乗せるのか、そんなことだけで充分にケンカの火種になる。カルチャー・ギャップをお互いに乗り越える過程がそのまま映画のストーリーになっていくんだよね。
外国映画でネタにされる日本の食といえば寿司とうどん。ローワン・アトキンソン主演「ジョニー・イングリッシュ」では何と回転寿司屋が登場。ついに外国映画にまで進出したか!って感じ。回転寿司といえば最近、うどんを出す店が出てきた。寿司屋でうどんはないだろう、と思っていたら、とんでもない話を聞いた。リドリー・スコット監督の傑作「ブレードランナー」の序盤で、ハリソン・フォードが屋台に入るシーンがある。あの屋台、てっきりうどん屋だと思っていたが、実はスシ・バーだという説があるのだ。確かに江戸時代には寿司は屋台で売っていた。あれがもし屋台の寿司屋で、サブメニューとしてうどんを出していたのだとすれば、リドリー・スコットは寿司の起源を理解した上、現代の寿司屋の姿をも予言していたことになる。うーん、リドリー恐るべし。
「ロスト・イン・トランスレーション」では、ズラッと並んだ日本人が次々ビル・マーレーに名刺を渡すシーンがある。「ガン・ホー」にもよく似たシーンがある。誇張はされているが、確かに日本人の名刺交換はあれだ。電話であやまる時は、姿が見えないのに頭を下げる。そうそう、やってるやってる。だって、あの方が声も謝ってるトーンになるんだもん。フランス映画では「TAXi2」で笑った。フランス人が言う…『僕は卓球が得意だ。温泉スポーツ。日本の心だ』。そう、温泉卓球は日本人の心だぞ、間違いなく。よく分かってるじゃん! 卓球そのものは誤解してるけど。
日本人を誤解してる、って日本人が思う映画はいろいろある。例えば「ライジング・サン」。日本企業のパーティで受付がみんな舞妓さん風の格好してるのを見て日本人は『あんなことしない!』って怒るんだけど、忘れちゃいけない、舞台はアメリカ。普通にスーツ着た男どもが迎えるより、きれいな舞妓さんが迎えた方がアメリカ受けするに決まってる。だから、あれで正しいのですよ。あれは”日本文化”ではなく、”日本から輸入した材料で作ったアメリカ文化”なのです。
そう、ちょうど”和製英語”と同じこと。英語圏の人から見れば奇異に見えるだろうけど、あれは英語ではなく”輸入した英語をもとに作った日本語”なのです。アメリカにアメリカン・コーヒーはない。だから日本人は間違ってる、と思ってはいけない。アメリカにはないアメリカン・コーヒーが、日本にあるってことが素晴らしいわけで。これがカルチャーギャップの楽しさなんだな。日本のゴジラは核エネルギーで生きているが、アメリカのゴジラは魚を食う。アメリカ文化の中では、日本産の怪獣はやっぱり魚を食った方がウケるのだった。いいのよ、面白けりゃ。
昔の映画に比べると、今の映画で登場する日本人はわりかしフツーになってしまった。「ティファニーで朝食を」でミッキー・ルーニーが演じたようなインチキ日本人はほとんど登場しない。その分、笑いの芸が細かくなっている。「ノッティングヒルの恋人」で、ホテルのフロントの男性にキスをしたヒュー・グラントを見て、後ろに並んだ日本人ビジネスマンが真似してキスしたのは笑った。これはもちろんギャグだけど、真似するのは大事なことだよね。それはカルチャーギャップを本当に理解するってことにつながる。だから、これを読んでいる外国人の皆さん、日本ではMcDonald’sをマクドナルドと発音してください。マクダネルズじゃ通じません。日本ではフリードリンク・フリーフードと書いてあってもタダじゃありません。そしてこの楽しいカルチャーギャップを大切にしましょう。それが、カルチャーギャップの迷路で迷子にならない方法なんですから。
************************************************************
去年~今年にかけて日本をテーマにした映画ラッシュが続いたことは記憶に新しい。話題になったあの2本をキネ万太郎氏が愛ある刀でシャキーンと斬る!
ラスト・サムライ
この映画は、外国で抱かれている日本人像を払拭した素晴らしい作品である。
1)日本人は頭にチョンマゲを乗せ、腰に刀を差していると思われてきたが、そんな人たちは官軍によって絶滅に追いやられたことがよく分かる。
2)日本人は意外に英語を喋れることがよく分かる。官僚だけでなく、侍の大将も、さらに天皇も美しい英語を喋っている。立派だ。
3)富士山が巨大な山であることがよく分かる。アメリカからの船が横浜港に着いたにもかかわらず、海岸沿いに堂々たる富士山が見える。現在では海岸線が埋め立てられているためかそうは見えないが、明治時代には横浜から眼前に見えたんだろうなあ…きっと。
キル・ビル vol.1
「ロスト・イン・トランスレーション」のアメリカ公開版では、日本語のセリフにも字幕がつかない。日本語が分からない主人公の気分がよりよく伝わるように、だ。一方「キル・ビル vol.1」では、ユマ・サーマンとルーシー・リューの掛け合いが日本語であるために、クライマックス・シーンであるにもかかわらず、何を言っているのか分からない。ぜひ字幕をつけてください。この映画の最大の魅力は、日本がいかに安全な国であるかがよく分かることだ。日本刀を持ったまま飛行機に乗っても咎められないほど、安全な国なのである。