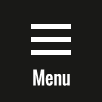Fukuoka Topics
- TOP
- Tag
- Fukuoka Topics

Jul 29, 2015 Now Reports
板付遺跡で学ぶ稲作の始まり
福岡市博多区の団地やマンションが立ち並ぶ住宅街に、緑に囲まれた公園のような施設があります。一見、普通の公園のようですが、実はここ、日本の稲作文化について知ることができる貴重な遺跡、国の史跡に指定された板付遺跡です。昭和25(1950)年に、縄文式土器と弥生式土器が一緒に出土したことから本格的な発掘が始まりました。

Jul 1, 2015 Now Reports
福岡で開催される柔道と剣道の全国大会
日本の高校のクラブ活動では古くからの武道が盛んに行われています。その代表格が柔道と剣道です。また、街中には小さな子どもたちも習うことができる柔道や剣道の道場があり、多くの子どもたちが通っています...

May 27, 2015 Now Reports
新しいウォーターフロントを目指して
福岡市の北側には海の玄関口・博多港があります。博多港は年間200万人もの乗降客が行き交う日本有数の港で、なんと乗降数は21年連続で日本一。また国際海上コンテナの取り扱い量も九州一を誇ります...

Apr 30, 2015 Now Reports
博多座界隈は江戸時代から芝居の中心地
歌舞伎、ミュージカル、演劇など、月替わりでさまざまな演目が上演される博多座。九州では最大級の劇場で、西日本一帯から芝居好きの観客が訪れます。あらゆる演目に対応できるよう、劇場に必要とされる「回り舞台」「花道」「袖花道」「奈落」「オーケストラピット」「鳥屋(とや)」などを備えていますが、これだけの設備がある劇場は全国でもめずらしいそうです。

Mar 27, 2015 Now Reports
人名に由来する天神の「渡辺通り」
福岡市の中心地・天神地区には南北を貫く「渡辺通り」があります。通り沿いには商業施設やオフィスビルが立ち並び、人も車も市内で有数の交通量を誇ります。なぜ、この通りを「渡辺通り」と呼ぶのかご存知でしょうか。実は、ある人物の名前に由来しているのです。

Feb 26, 2015 Now Reports
明治時代の洋館で文学を学ぶ
天神の一角、昭和通り沿いにある福岡市赤煉瓦文化館は、その名の通り、レンガの赤と白い帯、銅板葺の屋根が印象的な洋館。明治42(1909)年に日本生命保険株式会社九州支店として建てられた歴史ある建物で、国の重要文化財にも指定されています。以前は歴史資料館として使われていましたが、資料館の機能が福岡市博物館に移転したため、平成6(1994)年から赤煉瓦文化館として...

Jan 28, 2015 Now Reports
福岡の未来をつくる「創業特区」
福岡市は2014年3月に「国家戦略特区」のひとつに選定されました。「国家戦略特区」は地域を指定して規制緩和を進めることで、国際競争力のある産業を育てることを目的とした取り組みです。今回は全国で6つの地域が指定されましたが、応募総数197の地域から選ばれただけに、その期待の高さが伺われます。 福岡市が掲げているのは「創業特区」。新しい会社ができたり、新し...

Dec 22, 2014 Now Reports
天神の地名の由来となった天満宮
天満宮は学問の神様として名高い菅原道真を祭る神社のこと。とりわけ有名なのは道真が亡くなった場所にある太宰府天満宮ですが、このほかにも日本各地に天満宮があります。

Nov 28, 2014 Now Reports
クリスマス・イルミネーションもエコの時代
年末になると多くの人が楽しみにしている街角のイルミネーション。毎年クリスマスシーズンには、福岡のあちこちで工夫を凝らしたイルミネーションが登場して話題になります。まちづくり団体や商業施設が実施しているものが多いのですが、最近は個人で自宅にイルミネーションを装飾する人も多く、中にはプロ顔負けの仕上がりのものもあります。

Oct 27, 2014 Now Reports
歴史ある名島城跡とリンドバーグ
名島城は現在の福岡市東区名島にあった城です。慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いで貢献を認められ、豊前国中津から筑前国に移った黒田長政が最初に入った城でもあります。当時の名島城は三方を海に囲まれていたことから、長政は交通の便が良く、城下町が整備できる広い土地に拠点を移すことにします。これに伴い、名島城は慶長7年(1602年)に廃城となりました。